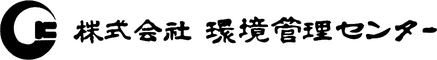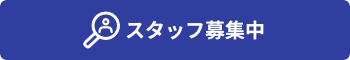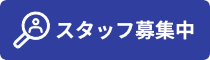| 総合案内 | 0235-24-1048 |
|---|
| ゴミ受付 | 0235-25-0801 |
|---|
| 窓口 | 8:30〜11:45/13:00〜16:30 |
|---|---|
| 電話対応 | 8:00〜12:00/13:00〜17:00 |
| 定休日 | 日・祝・土曜不定休・年末年始 |
- ホーム
- 環境管理センターブログ
- 玄関を出る瞬間に今日の出来は決まる?
玄関を出る瞬間に今日の出来は決まる?
2024/03/18
昨日は息子のテニスの試合で天童の総合運動公園にいました。あ〜寒かったー。会場では様々なお話しが繰り広げられて、特にお母さん達のお話っていうのは聞いているとほんと面白いです。その中で、ペットショップに行ったら九官鳥がいて、「にゃ〜」って鳴いてたとか、誰ですかそういういたずらしたのは。
小学生の頃学校に九官鳥がいて、みんな変な言葉を覚えさせていたのを思い出しましたが、にゃ〜と鳴く九官鳥、ちょと見てみたいですね。
今では片付け講師をしておりますわたくし小林ですが、子供の頃はといえば、鼻水垂らしてだらしのない、忘れ物常習犯の子供でした。親にプリントを出さない、もしくは当日の朝に出すという子で、ランドセルの中は常にもしゃくちゃしてましたね。現在の私を先生が知ったらおどろかれると思います。
それで今は、忘れ物っていうのはまずしなくなりました。忘れ物で相当痛いめを見てきたこともありますし、原因であった整理の滞りが解消されたからです。
忘れ物で一番効果を発揮するのは、出かける際必要となるモノのグルーピングと鞄の中身の定位置管理です。出かけるまでの動線をチェックして最短の移動距離でその動線上に必要となるものをできるだけ固めて配置する。こうすると時短で忘れ物も防止できます。
あとは鞄の中身。鞄の中身は常に最適化を図り、軽く・アイテム数を絞るということを念頭に、ブラインドタッチで何がどこに収納されているのかわかるレベルに仕上げる。鞄から出してまた戻すのストレスと最低限にすれば、忘れ物を防止できます。
鞄を変えた時、忘れ物リスクが高まります。これを防止する策として以前はバッグインバッグで対応していたのですが、よく考えたら、これ鞄に失礼なんじゃないかって思ったんです。せっかく収納なりポケットなりがついていて、入れ物として完結しているのに、そこにさらにバッグ入れてこられたら自分が鞄の立場だったら面目丸潰れです。だから、とにかくアイテム数を絞る。こうしたら鞄を変えるのも楽だったんです。
さあ今日という日をどう生きるのか、玄関を出る瞬間にすでに決まっているのかもしれません。
関連エントリー
-
 805/1000 鈍刀を磨く人生
「鈍刀を磨く。」という言葉を知った。自分を磨く、という言葉は少し気恥ずかしい。どこか意識が高い感じもするし、成
805/1000 鈍刀を磨く人生
「鈍刀を磨く。」という言葉を知った。自分を磨く、という言葉は少し気恥ずかしい。どこか意識が高い感じもするし、成
-
 807/1000 空き家と積雪
今日は立春ということで、日差しがほんの少しだけ柔らかく感じられる一日だった。今年は、凍てつくような寒さというほ
807/1000 空き家と積雪
今日は立春ということで、日差しがほんの少しだけ柔らかく感じられる一日だった。今年は、凍てつくような寒さというほ
-
 807/1000 最後の40代を丁寧に
鶴岡市から山形市までは、およそ90km。車で走ると、だいたい2時間ほどかかる。普段は庄内総合支庁に伺うことが多
807/1000 最後の40代を丁寧に
鶴岡市から山形市までは、およそ90km。車で走ると、だいたい2時間ほどかかる。普段は庄内総合支庁に伺うことが多
-
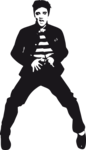 809/1000 ロックスターのサブスクマーケテイング
ロックスターには、つい神秘を求めすぎてしまう。ずっと不良で、心に傷を負っていて、社会にうまく回収されず、それで
809/1000 ロックスターのサブスクマーケテイング
ロックスターには、つい神秘を求めすぎてしまう。ずっと不良で、心に傷を負っていて、社会にうまく回収されず、それで
-
 811/1000 グルテンフリーと霜焼けの意外な関係
この冬、私にとってはっきりとした変化があった。毎年、足の指が凍傷レベルの地獄の霜焼けに悩まされてきた。歩くのが
811/1000 グルテンフリーと霜焼けの意外な関係
この冬、私にとってはっきりとした変化があった。毎年、足の指が凍傷レベルの地獄の霜焼けに悩まされてきた。歩くのが