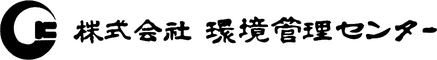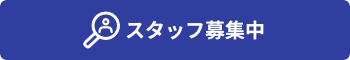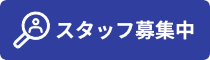| 総合案内 | 0235-24-1048 |
|---|
| ゴミ受付 | 0235-25-0801 |
|---|
| 窓口 | 8:30〜11:45/13:00〜16:30 |
|---|---|
| 電話対応 | 8:00〜12:00/13:00〜17:00 |
| 定休日 | 日・祝・土曜不定休・年末年始 |
- ホーム
- 環境管理センターブログ
環境管理センターブログ
805/1000 鈍刀を磨く人生
2026/02/02
「鈍刀を磨く。」
という言葉を知った。
自分を磨く、という言葉は少し気恥ずかしい。
どこか意識が高い感じもするし、成果が出ていないときほど、口にしづらい言葉だ。
でも実際は、もっと地味で、もっと日常的なものだと思っている。
毎日、必ずひとつ。
「あ、ここだな」と感じるポイントが訪れる。
人とのやり取りだったり、仕事の段取りだったり、
自分の言い方や態度だったりする。
大きな事件ではない。
むしろ、誰にも気づかれないような小さな場面だ。
その瞬間に、ふっと思う。
――ああ、今日も試されているな、と。
正解を出す試験ではない。
速さや要領を競うテストでもない。
「どう振る舞うか」「どう受け取るか」「どう飲み込むか」。
そんな、人としての姿勢を問われているような感覚だ。
鈍刀はいくら磨いても光らない。しかし磨いた自分が磨かれる。
人は何を鈍刀とするのかで、人生が変わるのだろう。
もちろん、渦中にいるときはしんどい。
またか、と塞ぎ込みたくなる日もある。
それでも結局、またここに戻ってきてしまう。
どうやら、
鈍刀を磨くという愚行をやめない人生を、
選んでしまったらしい。803/1000 高いところを片づける
2026/01/31
毎年恒例の、高所作業車でのクモの巣取り。
暮れの大掃除ではどうしても手が回らず、年を越してからの作業になるのが、ここ数年の流れだ。
工場の天井は高い。
脚立では届かず、12メートルの高所作業車を借りて行う。
下から見上げていると大したことがないように思えるが、いざ上がってみると、なかなかの高さだ。
クモの巣を一つずつ取り除いていく。単純な作業だが、高さのせいか、気は抜けない。
このクモの巣取りが終わらないと、どこかにやり残し感が残っていた。
見えない場所に残ったままのものが、頭の片隅に引っかかっている感じだ。
だから毎年、これを終えるとようやく一区切りがつく。
せっかくなので、この際とばかりに、高い場所の小さな修理も済ませた。
こういう時に助けになるのが、前職で取得した資格だ。
群馬県まで行かせていただいて、同僚と新幹線に乗って取りに行った。
今思えば、あれはちょっとした小旅行のようで、なかなか楽しい思い出でもある。
当時は、いつ使うかも分からずに取った資格だった。
それがこうして、今の仕事の中で役に立っている。
過去の時間や経験が、形を変えて今につながる瞬間は、静かにうれしい。
明日から二月。とにかく寒い。
それでも、陽は確実に長くなっている。
夕方、工場の外に出たときの空の明るさが、ほんの少し違う。
春用のコートは、もう買ってある。
まだ出番は先だと分かっているが、クローゼットを開けるたびに目がいく。
クモの巣がなくなった工場で、次の季節を迎える準備は、たぶん整った。
春は、もう来ている。
まだ空気は冷たいけれど。
801/1000 経営というメンコ合戦
2026/01/29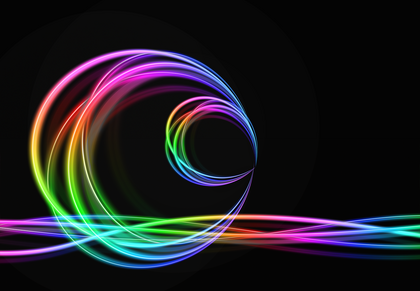
東京出張二日目。
中期経営計画を立てる勉強会に参加している。利益、戦略、数字、未来。
ノートを取りながら、改めて目にとまったのはドラッカーの言葉だった。
「企業の目的は顧客の創造」
そして、企業の基本的な機能は二つだけ。マーケティングとイノベーション。
成果をもたらすのも、この二つだけで、それ以外はすべてコストである、と。
ここでいう成果とは、売上や利益のことではない。
成果の本質は、外の世界に変化を起こすこと。
売上はいくらか。利益はいくら残ったか。
もちろん大事だ。でもそれは結果であって、目的ではない。
本当に問うべきなのは、
お客様はどう良くなったのか。
社員はどう良くなったのか。
ここが抜けた瞬間、経営は数字遊びになる。
売上を伸ばした。規模を大きくした。競合に勝った。
それはどこか、子どもの頃のメンコ合戦に似ている気がした。何枚取ったか、誰に勝ったか。場が終われば、残るのは数だけだ。
でも経営は、本来メンコを集める遊びじゃない。
関わる人の現実が、昨日より少し良くなること。
その積み重ねの先に、たまたま数字がついてくる。
仏教に「自利利他」という言葉がある。
自分だけでなく、他者も良くなる。ドラッカーの言う成果と、同じ匂いがする。
二日目の勉強会で増えたのは、ノウハウよりも問いだった。
社長の仕事とは何か。
経営というメンコ合戦から、そろそろ降りてもいい頃なのかもしれない。
799/1000 どれだけ少なく、どれだけ軽く
2026/01/27
797/1000 変化の春が待ち遠しい。
2026/01/25
今日は習字の練習日だった。
師匠から、ありがたくも初段合格のお祝いの筆を頂き、すぐ使わせてもらった。
弘法筆を選ばず、と言う。名人は道具のせいにしない、という意味の言葉だ。
逆に言えば、もう筆のせいには出来ない。
師匠からこんな素敵な筆を頂いてしまった以上。
とはいえ、この筆がまた書きやすい。
ずっしり重みがあり、毛先がしなやかだ。ミニバンからスポーツカーに乗り換えたような、ハンドリングの楽しさがある。線を引くと、筆がスッと進み、止めいたいところで止まった。
字は正直だ。
調子のいい日は、それなりの線になる。
気が散っている日は、それなりに出る。
ハンドリングがいい分、悪い癖なんかもそのまま出てしまうだろう。
練習を終えて帰る道すがら、冬物のセール、モアセール開催中の案内がメールに何通も届く。
狙っていたコートは結局セールにはならなかったが、思い切ってポチッと買うことにした。
これまで似合わないと思って、避けてきた色と形だ。
習字の目標と共に、こちらも今年の目標に入れていたものだ。
変化を楽しめる春が待ち遠しい。
-
 891/1000 見えない壁をぶち壊す
当社ではここ数年かけて、事務所の書類をすべて見直してきた。棚にあるもの、倉庫にあるもの、個人の机の中にあるもの
891/1000 見えない壁をぶち壊す
当社ではここ数年かけて、事務所の書類をすべて見直してきた。棚にあるもの、倉庫にあるもの、個人の机の中にあるもの
-
 793/1000 夢が手触りを持った日
令和七年一月一日。私は七つの目標を立てた。手帳の最初のページに書いたそれらは、正直に言えば、かなりぼんやりして
793/1000 夢が手触りを持った日
令和七年一月一日。私は七つの目標を立てた。手帳の最初のページに書いたそれらは、正直に言えば、かなりぼんやりして
-
 795/1000 二度寝をやめて、マインドセットから解放されたい
人は、決めつけて楽になりたい生き物だと思う。世の中はこういうものだ、自分はこういう人間だ、今日はこういう一日だ
795/1000 二度寝をやめて、マインドセットから解放されたい
人は、決めつけて楽になりたい生き物だと思う。世の中はこういうものだ、自分はこういう人間だ、今日はこういう一日だ
-
 797/1000 ふりかけと白米
面白い記事を読んだ。近年、ご飯にかける「ふりかけ」の消費量は増えているのに、肝心の「米」の消費量は減っていると
797/1000 ふりかけと白米
面白い記事を読んだ。近年、ご飯にかける「ふりかけ」の消費量は増えているのに、肝心の「米」の消費量は減っていると
-
 797/1000 変化の春が待ち遠しい。
今日は習字の練習日だった。師匠から、ありがたくも初段合格のお祝いの筆を頂き、すぐ使わせてもらった。弘法筆を選ば
797/1000 変化の春が待ち遠しい。
今日は習字の練習日だった。師匠から、ありがたくも初段合格のお祝いの筆を頂き、すぐ使わせてもらった。弘法筆を選ば