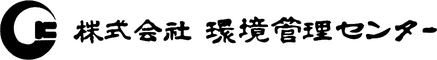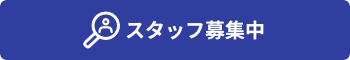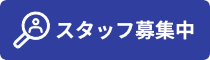| 総合案内 | 0235-24-1048 |
|---|
| ゴミ受付 | 0235-25-0801 |
|---|
| 窓口 | 8:30〜11:45/13:00〜16:30 |
|---|---|
| 電話対応 | 8:00〜12:00/13:00〜17:00 |
| 定休日 | 日・祝・土曜不定休・年末年始 |
- ホーム
- 環境管理センターブログ
環境管理センターブログ
787/1000 必要なのは、答えではない。変化だ
2026/01/13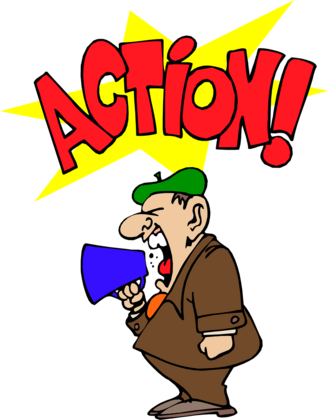
お片づけの現場に立っていると、ときどき首をかしげることがある。
なぜ、この家のボトルネックが見えないのだろう。
なぜ、打開策が立たないのだろう。
物の量の問題でも、収納の問題でもない。
明らかに流れが止まっている場所がある。
けれど話を伺っていくと、いつの間にか全く関係のない「自分はこういう人間で」という話になり、できない理由が次々と積み上がっていく。
この光景は、業務改善の現場とまったく同じだ。
工程の話をしているはずなのに、性格の話になり、忙しさの話になり、昔話になる。
現象は語られるのに、構造には触れられない。
人は不思議なほど、同じ場所で滞り、同じ場所でつまずく。
話を聞きながら、ときどき思ってしまう。
本当に見えていないのだろうか。
それとも、見ないようにしているのだろうか、と。
ボトルネックが見えた瞬間から、現実は動き出す。
決めなければならないことが生まれ、変えなければならないことが現れる。
自分のやり方に手を入れる必要が出てくる。
人はそれを、本能的に知っているのかもしれない。
だから話は、自称に流れる。
事情に流れる。
できない理由に流れる。
けれど、お片づけも業務改善も、突き詰めればとてもシンプルだ。
変えられるのは、自分しかいない。
ここに気づいたとき、世界の見え方が変わった。
そして同時に、これはとても楽しいことだとも思った。
自分の頭で考える。
小さく動いてみる。
置き場を変える。
聞き方を変える。
順番を変える。
すると必ず、何かが起こる。
部屋が変わらなくても、会話が変わる。
会話が変わらなくても、見え方が変わる。
見え方が変われば、次の一手が生まれる。
動けば、必ず変化は起こる。
多くの人が欲しがるのは「答え」だ。
正解が欲しい。
これをやればうまくいく、という地図が欲しい。
けれど現場に立っていると、はっきりしてくる。
答えなんて、いつも変わっていく。
暮らしが変われば、正解も変わる。
会社が変われば、やり方も変わる。
自分が変われば、見える世界が変わる。
昨日の答えは、今日の前提にはならない。
だから私は、答えを出して終わりにしたくないと思っている。
答えを出して、思考を止めるな。
答えは仮置きでいい。
それよりも、動き続けること。
試し続けること。
変化を起こし続けること。
お片づけも、業務改善も、経営も、暮らしも、
必要なのは「正しさ」より「動き」なのだと思う。
動かせる自分でいること。
更新できる自分でいること。
必要なのは、答えではない。
変化だ。785/1000 息子とベースを買いに行った話
2026/01/11
高1の息子と楽器屋に言った。ベースを買うためた。
私は高校一年のときにギターを始めた。
だから、息子が高校の音楽クラブでベースをやりたいと言った時、始めるには、いいタイミングだと思った。
二人で楽器屋へ行き、壁一面に並ぶギターやベースの前に立つ。息子は急に無口になり、目だけが忙しく動く。何本か触るうちに、一本、やけに手に馴染むものがあった。
値札を見る。
……予算の二倍。
ん〜どうしよう。
一旦、家に帰ろう。
ショップにいると、冷静な判断ができなくなる。これは自分の経験でよく知っている。
家に戻り、妻に相談する。三人で話す。すると息子が、「俺も出す」と言って、貯めていた虎の子を出すと言う。
私はこれまで、何を手にするかで、その後の取り組みが変わる場面を何度も見てきた。
「一本目は妥協するな」
これは、一本目に限った話ではないのかもしれない。
予算も、分相応も、もちろんある。
その中で妥協すると、それは後悔になる。
とくに、趣味の物なら、なおさらだ。
それで、決めた。
一本目にしては、かなり上等なベースを手に入れた。
家に帰ってアンプにつなぐ。
ぼん。
低くて、丸い音。
ここからだな、と思った。
チューニングメーターの使い方、アンプのセッティングやフォームを軽く教える。私がギターを始めた頃は、チューニングができて音が出るようになるまで一か月かかった。それが息子は一時間。
息子の学校で出された課題曲は、モンゴル800の「小さな恋のうた」だという。
発表は、一か月後。
それを見ていた末の娘が言った。
「私、ドラム買ってほしい。」
……なるほど。
うれしい悲鳴、というやつかもしれない。
このベースが、埃をかぶって、しまい込まれるか。
それとも、一生の趣味になるのか。
それは、まだ分からない。
私もかつて、父に連れられて、仙台の楽器屋でギターを買ってもらった。
その日のことを、私は今でもはっきり覚えている。
今日が、息子にとっても、
そんな一日になってくれたらと思う。783/1000 便利で気の毒な社会
2026/01/09
今日は、市役所と税務署に行った。
用事自体は、よくある事務的なものだ。
けれど建物に入った瞬間、手続きより先に、ある風景が目に入った。
多い。とにかく高齢の方が多い。
椅子に座り、番号札を握り、窓口を見つめている背中が並んでいる。
「こちらはLINEで登録していただいて、予約してからになります」
「マイナンバーの暗証番号、分かりますか?」
窓口の向こうで、担当の方がやさしい声で聞いている。
もちろん、高齢の方は分かっていない。
それは怠けているからでも、努力が足りないからでもない。
ただ、その仕組みが、その人の人生の速度と噛み合っていないだけだ。
後ろを見ると、列はどんどん伸びている。
誰も怒っていない。
誰もサボっていない。
みんな真面目で、ちゃんとしようとしている。
だからこそ、そこに漂っていたのは苛立ちではなく、
全員が、少しずつ気の毒な空気だった。
印象的だったのは、説明している担当者の方の表情だ。
彼は相手にこの情報が伝わっていないことを理解している。
私たちも、高齢者の依頼者が多い。
中には、自分の住所が言えない人もいる。
カレンダーに書いてある電話番号を見て、
「これ、何の番号だったかな」と言いながら、
粗大ごみの依頼を忘れて電話を日に何度もかけてくる人もいる。
誰かの助けがないと、
もう手続きどころか、
日常そのものが成り立たない人たち。
そしてその「誰か」は、
家族だったり、近所の人だったり、
ケアマネさんだったり、
そして時々、私たちだ。
実は私自身も、電子申請にチャレンジはする。
けれど結局、紙で出していることが多い。
正直に言えば、それが本物なのか、詐欺なのか、
一瞬わからなくなることもある。
分かっていない人。
分からせられない人。
ついていこうとしている人。
今日の窓口は、これからの社会の仕事風景そのものだった。
仕組みが先に進み、
人の速度が、少し遅れている。
その間に立って、
今日も誰かが、説明し、聞き、支えている。
便利で気の毒な社会だ。
781/1000 熊と雀のあいだ
2026/01/07
鳥獣被害という言葉の中には、クマの被害も含まれている。
庄内でもクマの出没情報は珍しくなくなり、ニュースになるたび、空気が一段重くなる。
イノシシやシカは畑の話になるが、
クマは命の話になる。
クマにも命があるということは、誰しもが思うところだ。
それでもクマは、ニュースになり、警戒情報が出て、出動要請が出て、銃が向けられる。
その事実の前では、正しさはいつも、いくつも並ぶ。
そんなことを考えながらも、
我が家の軒先には、今日もスズメがやってくる。
十羽ほどだろうか。
実は鳥の餌を撒いている。完全にこちらの都合なのだが、それがまた可愛い。
懐くわけではない。
近づけば一斉に飛び立つ。
それでも必ず来て、来ると決まって賑やかだ。
ピチピチと鳴きながら、
小さな体で場所取りをして、
誰かが追い出されて、誰かが割り込んで。
ある日、妻がふと気になって、スズメの寿命を調べた。
一年ほどだという。
その数字を見たとき、少しだけ、スズメの見え方が変わった。
一年の命。
毎日来ているこの中に、
もう春を迎えられないやつもいるのかもしれない。
そんなことを考えたこともなかった。
今日も雪の上に、意外と大きな足跡を残して、スズメたちがやってきた。
人と野生の関係は、いま、そのちょうど難しいところに来ている気がする。
それでも雪の上の小さな足跡を見ていると、
被害の前に、
管理の前に、
まず「生きている」があるのだと、思わされる。779/1000 静かに始まる一年
2026/01/05
本日、仕事始め。
一年が、静かに動き出した。
朝から降っていたのは、ぼたぼたと重たい雪。
いかにも庄内の冬らしい雪だな、と思いながら会社に向かう。
けれど駐車場は、すでにきれいに除雪されていて、すんなり車を停めることができた。
休み中に、スタッフが手を動かしてくれていたのだ。
こちらが何かを言わなくても、
必要なことを感じ取って、動いてくれる人がいる。
これはもう、はっきり言っていいと思う。
すみません、自慢です。
仕事というのは、結局のところ「人」だ。
制度や仕組みも大切だけれど、
最後に現場を支えるのは、こういう行動だと思っている。
正月に帰省していた娘たちは、それぞれに東京へ戻っていった。
家の中は、少しだけ静かになった。
寂しさがないわけではないが、
それぞれの場所に戻っていくのが、今の家族のかたちなのだろう。
今回の正月は、久しぶりに家族そろって紅白歌合戦を観た。
「この人たち、みんな同じ顔に見えるんだけど。俺だけ?」
そんな一言に、娘たちが一斉に反応する。予想通りのリアクション。
それでも、
「やっぱり、えーちゃんはかっこいい」
となると、そこは意見がそろう。
そして小林家恒例のモノポリー大会も、例年通り。
今年は、私が大勝ち。
流れが来る年というのは、こういうところにも表れるらしい。
勝った負けたはさておき、
同じテーブルを囲んで、同じ時間を過ごすこと自体が、もうイベントなのだ。
紅白も、おせちも、モノポリーも。
みんなで観る。
みんなで食べる。
みんなで楽しむ。
だから、もっと楽しい。
派手な正月ではないが、
こういう時間があることを、素直にありがたいと思う。
帰り際、娘たちをグッとハグして見送った。
特に言葉は交わさなかった。
家族がそれぞれの場所へ戻り、
会社では、信頼できるスタッフと一緒に、新しい一年が始まる。
静かだが、足元はしっかりしている。
今年は、そんなスタートだ。-
 793/1000 夢が手触りを持った日
令和七年一月一日。私は七つの目標を立てた。手帳の最初のページに書いたそれらは、正直に言えば、かなりぼんやりして
793/1000 夢が手触りを持った日
令和七年一月一日。私は七つの目標を立てた。手帳の最初のページに書いたそれらは、正直に言えば、かなりぼんやりして
-
 795/1000 二度寝をやめて、マインドセットから解放されたい
人は、決めつけて楽になりたい生き物だと思う。世の中はこういうものだ、自分はこういう人間だ、今日はこういう一日だ
795/1000 二度寝をやめて、マインドセットから解放されたい
人は、決めつけて楽になりたい生き物だと思う。世の中はこういうものだ、自分はこういう人間だ、今日はこういう一日だ
-
 797/1000 ふりかけと白米
面白い記事を読んだ。近年、ご飯にかける「ふりかけ」の消費量は増えているのに、肝心の「米」の消費量は減っていると
797/1000 ふりかけと白米
面白い記事を読んだ。近年、ご飯にかける「ふりかけ」の消費量は増えているのに、肝心の「米」の消費量は減っていると
-
 797/1000 変化の春が待ち遠しい。
今日は習字の練習日だった。師匠から、ありがたくも初段合格のお祝いの筆を頂き、すぐ使わせてもらった。弘法筆を選ば
797/1000 変化の春が待ち遠しい。
今日は習字の練習日だった。師匠から、ありがたくも初段合格のお祝いの筆を頂き、すぐ使わせてもらった。弘法筆を選ば
-
 799/1000 どれだけ少なく、どれだけ軽く
明日から二泊三日の東京出張に備えて、段取り中。 大雪の庄内から晴天であろう東京へ行くので、まず靴から考える。
799/1000 どれだけ少なく、どれだけ軽く
明日から二泊三日の東京出張に備えて、段取り中。 大雪の庄内から晴天であろう東京へ行くので、まず靴から考える。