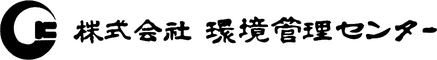| 総合案内 | 0235-24-1048 |
|---|
| ゴミ受付 | 0235-25-0801 |
|---|
| 窓口 | 8:30〜11:45/13:00〜16:30 |
|---|---|
| 電話対応 | 8:00〜12:00/13:00〜17:00 |
| 定休日 | 日・祝・土曜不定休・年末年始 |
- ホーム
- 環境管理センターブログ
環境管理センターブログ
777/1000 何者かにならなくてもよかったのだと、気づく瞬間
2026/01/03
年始から、ひとつだけ続けていることがある。
それはギターだ。
ギターを始めたのは高校時代。
そもそものきっかけは、とてもささやかなものだった。
母親がフォークミュージックが好きで、
「弾いてくれたら嬉しいな」
子どもの頃に、そんなことをぽろっと言ったのを覚えている。
その一言に応えたくて、ギターをやってみようと思った。
だから本当は、アコースティックギターを弾きたかった。
ところが高校に入って、クラスメイトに
「ギターって何から始めればいい?」
と聞いたら、返ってきたのは
「俺の家来い」
の一言。
そこで初めて見せられたのが、エレキギターだった。
当時はバンドブーム。
ギターを手にする若者は山ほどいた。
そしてその多くが、きっとそうだったように、
“何者かになろう”としてギターを持っていたんじゃないかと思う。
気がつけば私も、最初のきっかけなんてすっかり忘れて、
クラスメイトと一緒に、何者かになろうとしてギターを練習していた。
結局、何者にもなれないまま、
あの頃の時間はあっという間に終わってしまった。
ただ、不思議なことに、
その火種だけは消えなかった。
大した上達もしないまま、
ギターはずっとそばにあって、
年月だけが静かに過ぎていった。
そして今年。
その燻りに、いったん終止符を打とうと思った。
ギターを手放そう。
そう決めたのだ。
数年前に購入した、とびきり素敵な一本がある。
壁に飾っておくには、あまりにももったいない。
相当に吟味して選び抜いた、素晴らしいギターだ。
それをインテリアにしてしまうのは、どうにもかわいそうだった。
手放そうと考えたとき、
ふと、ひとつのことに気がついた。
――自分は、ギターで何者かになろうとしていたんじゃないか。
高校時代のマインドセットが、
ギターを弾くことそのものを、
つまらなくしていたんじゃないか。
手放そうとしなければ、
きっと一生気づかなかったことだと思う。
そう気づいた途端、
不思議とギターが素直に弾きたくなった。
正月は、毎日ギターに触れていた。
そして、
「なぜギターを弾きたかったのか」
その初心を、ようやく思い出した。
今年の目標のひとつに、
両親(私の両親、妻の両親)四人を招いて、
長寿のお祝いをする、というイベントがある。
その場で、
母が好きだった「なごり雪」を
ソロギターで弾く。
そんな目標が、自然と生まれた。
何者かになろうとする気持ちは、
形を変えながら、これまでずっと自分の中にあった。
けれど、その気持ちが
すっかり消えていることに、
手放すことで気がついた。
何者かになる必要はない。
たぶん、もうなっている。
自分として生きる。
それは、自分を受け入れられた時に始まるのだろう。
今年は、そんな元年なのかもしれない。
なんとも言えず、
爽快な気分でいる。
775/1000 新年一発目は、ピント合わせから
2026/01/01
新年が始まりましたね。
朝起きて、まずやったことは、やっぱりお片づけでした。
とはいえ、普段からそれなりに片付けているつもりではあります。
でも、ふとした瞬間に「今だな」とスイッチが入って、やり始める。
新年という区切りは、やっぱりそのきっかけになります。
今日は、いつも仕事で使っているバッグにバッグフォルダーを設置しました。
それから、娘のバレーボール部引退に伴って、あまり出番のなくなった自慢の望遠レンズの置き場を変更したり。
どれも大きな変化ではありませんが、一年の中で環境は確実に少しずつ変わっている。
その変化に、こちらの感覚を合わせ直していくような時間でした。
これは、メガネを新調したときの感覚に少し似ています。
それまで特別ぼやけているとは思っていなかったのに、新しいメガネに替えた瞬間、世界がくっきりと見え始める。
「ああ、こういう輪郭だったのか」と、あとから気づくあの感じです。
お片づけも同じで、困っているわけじゃない。
不便でもない。
ただ、ほんの少し整えるだけで、動きが滑らかになり、気持ちまで静かになる。
使わなくなったから手放す、というほどでもない。
けれど、今の暮らしや仕事の動線には、少しだけ合わなくなってきたモノたち。
だから、役割に合わせて居場所を変える。
お片づけをしていると、モノを整理しているようで、
実は家族の時間や、自分のステージの変化をそっと確認しているのだなと思うことがあります。
新年一発目は、やっぱりお片づけから。
何かを大きく変えるというより、「今の自分に、きちんとピントを合わせる」。
そんなスタートが、今年はちょうどいい気がしています。773/1000 末広がりで、年を終える
2025/12/30
当社は今日で御用納め。
とはいえ、明日31日も数名のスタッフが出勤してくれる。年末の区切りというのは、きれいに線が引かれるものでもないのだと、そんなことを思う。
それにしても、今年の冬はやけに暖かい。
正月前のあの張りつめた空気や、凛とした寒さがなくて、「ああ、もう年が変わるんだな」という実感が、どうにも湧いてこない。私だけだろうか。
そんな中、義母から電話があった。
子どもたちにお年玉を8,000円ずつ送ったという。
「なんだか半端だね」と妻が言うと、その理由が面白かった。
来年は令和8年。末広がりの「8」だから、8,000円なのだそうだ。
なるほど、そういう願いの込め方もあるのかと、少し嬉しくなる。
今年最後の買い物は、コンビニで済ませた。
レジで受け取ったレシートを何気なく見ると、合計金額は888円。
これはなんとも景気がいい。
願掛けのような気持ちでそのレシートを持ち帰り、小林家のグループLINEにアップした。
振り返れば、今年もいろいろあった。
ただ、不思議なことに、今年ほど自分を成長させてくれた年はなかったように思う。
思い通りにいかない出来事も、立ち止まった時間も、あとになってみれば、すべてが自分をつくる養分になっていた。
今はまだ、その成長がはっきりとした形になっているわけではない。
けれど、この一年で積み重ねてきたものが、来年きっと花をひらく。
そう信じて、新しい年を迎えたい。
派手さはないけれど、悪くない年の締めくくりだ。
静かに、そして前を向いて、今年を終える。771/1000 庄内お片づけ部忘年会開催
2025/12/28
昨日は、地域にお片づけの魅力を発信していこうという、稀有な団体、庄内お片づけ部の忘年会がありました。
年末らしく、まずは今年の活動を振り返るところから話は始まります。
整理収納アドバイザー東北フォーラムのホストを務めたり、無印良品酒田にブース出店したりと、忙しくも手応えのある一年でした。
その渦中にいるときは余裕がなくても、こうして年の終わりに言葉にしてみると、「ちゃんと前に進んでいたな」と静かに実感します。
話題は自然と映画の話へ。
庄内お片づけ部は、私以外は全員女性。
同じ映画を観ていても、登場人物の感情の揺れや、言葉にされなかった背景に目を向ける視点がとても細やかで、聞いているだけで視界が少し広がる感覚があります。
スクリーンに映っていたのは同じはずなのに、見えていた景色はそれぞれ違っていたようです。
それで、2枚目も好きなんだけど、映画でいちばん印象に残るのは、2.5枚目だったりする話とか。納得でした。
完璧すぎる主人公より、ちょっと格好よくて、でもどこか抜けている。決めきれない場面があったり、余計な一言を言ってしまったり。
その“0.5枚分の人間味”がある登場人物こそ、エンドロールの後にふと思い出される存在だったりします。
そのまま話題は波動の話だったり、スピリチュアル界隈では来年は流れが変わるらしい、なんて話まで。
とはいえ、どれも肩に力の入った話ではなく、片づけも、映画も、スピリチュアルな話も、結局は
「今の自分は、どんな状態で生きているのか」それを確かめる時間だったように思います。
にぎやかではないけれど、心地いい。
今年をきちんと終えて、少しだけ前を向けた、そんな忘年会でした。769/1000 今年最後の儀式
2025/12/26
私は父の会社を継いだから、
仕事というのは、これしかないと思ってきた。
それでも、ときどき思う。
本当は、自分は何をしたいのだろう、と。
腕時計が好きだから、
「65歳になったら、時計屋さんにでもなろうかな」
と妻に言う。
「儲からなそう」
そう言って、妻は笑う。
でも私は知っている。
父から受け継いだのは、清掃という仕事だ。
そしてこの仕事をしているとき、
自分はいちばん幸せだということを。
楽な仕事ではない。
無理をすることもあるし、
しんどい現場もある。
それでも、現場に立っていると、
自分がちゃんと、ここにいる感覚がある。
私は、この仕事が好きだ。
そしてここが、
私がいちばん、活きる場所だ。
今年最後の空家整理の現場が終わった。
空き家から、どんどんモノが運び出されていく。
掃除機で、タンスの裏に溜まった
ヤニの混じった綿ぼこりを吸い、
ネズミのフンを箒で集めていく。
そうしているうちに、
家そのものが、深呼吸を始めるのが分かる。
この家は、解体されるという。
それでも、最後は掃き清める。
解体前の空家を、ここまで丁寧に清掃する業者は多くない。
ご依頼主から、特別な指示があるわけでもない。
けれど、これは私たちにとって大切な儀式だ。
ここにあった想い出を、
どこか天国みたいな場所へ送り出すための、儀式だ。
そんな、今年最後の儀式が終わった。
-
 891/1000 見えない壁をぶち壊す
当社ではここ数年かけて、事務所の書類をすべて見直してきた。棚にあるもの、倉庫にあるもの、個人の机の中にあるもの
891/1000 見えない壁をぶち壊す
当社ではここ数年かけて、事務所の書類をすべて見直してきた。棚にあるもの、倉庫にあるもの、個人の机の中にあるもの
-
 793/1000 夢が手触りを持った日
令和七年一月一日。私は七つの目標を立てた。手帳の最初のページに書いたそれらは、正直に言えば、かなりぼんやりして
793/1000 夢が手触りを持った日
令和七年一月一日。私は七つの目標を立てた。手帳の最初のページに書いたそれらは、正直に言えば、かなりぼんやりして
-
 795/1000 二度寝をやめて、マインドセットから解放されたい
人は、決めつけて楽になりたい生き物だと思う。世の中はこういうものだ、自分はこういう人間だ、今日はこういう一日だ
795/1000 二度寝をやめて、マインドセットから解放されたい
人は、決めつけて楽になりたい生き物だと思う。世の中はこういうものだ、自分はこういう人間だ、今日はこういう一日だ
-
 797/1000 ふりかけと白米
面白い記事を読んだ。近年、ご飯にかける「ふりかけ」の消費量は増えているのに、肝心の「米」の消費量は減っていると
797/1000 ふりかけと白米
面白い記事を読んだ。近年、ご飯にかける「ふりかけ」の消費量は増えているのに、肝心の「米」の消費量は減っていると
-
 797/1000 変化の春が待ち遠しい。
今日は習字の練習日だった。師匠から、ありがたくも初段合格のお祝いの筆を頂き、すぐ使わせてもらった。弘法筆を選ば
797/1000 変化の春が待ち遠しい。
今日は習字の練習日だった。師匠から、ありがたくも初段合格のお祝いの筆を頂き、すぐ使わせてもらった。弘法筆を選ば