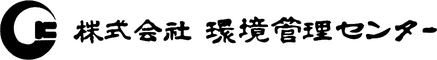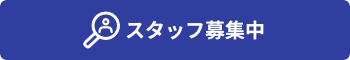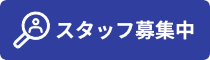| 総合案内 | 0235-24-1048 |
|---|
| ゴミ受付 | 0235-25-0801 |
|---|
| 窓口 | 8:30〜11:45/13:00〜16:30 |
|---|---|
| 電話対応 | 8:00〜12:00/13:00〜17:00 |
| 定休日 | 日・祝・土曜不定休・年末年始 |
- ホーム
- 環境管理センターブログ
- 18/1000 不要なモノの歴史はまだ50年
18/1000 不要なモノの歴史はまだ50年
2024/04/09
プラスチックなどの人工合成物があまりなかった50年ほど前には、日本では不要となる物があまり無くて、ゴミっていう括り方・捉え方が弱かったんだそうです。それから大量生産・消費社会になって、毒性があるとか、健康を害するとかいう理由で、廃棄物っていう考え方が生まれて行った。だからゴミ・廃棄物の歴史って実は浅いんです(環境管理センター、当社は今期で48期を迎えたのですが、まさにこの廃棄物という概念が生まれた時代に誕生していることが分かります。)。
その歴史の浅さにも起因すると思いますが、その物が有価物なのか廃棄物なのかっていう判断には社会全体曖昧なところがあります。
誰かにとっては宝物でも誰かにとっては不要物なんていうモノって家の中を見渡してみてもたくさんありますし、それでどうやってゴミかそうでないのかっていう判断をするのかっていうと法律的にも歴史の中で紆余曲折あって、現在は「総合判断説」という所に落ち着いています。
それは、①物の性状 ②排出の状況 ③通常の取扱形態 ④取引価値の有無 ⑤占有者の意志 の5つを総合的に判断して有価物か廃棄物かを判断する、と法では定めています。そうやらないと分からないっていうぐらい実はゴミって曖昧。
だからお片付けなんかして要・不要の区別が難しいなんていうのは当たり前のこと、上手くできないくて当然。
ゆえに、明確な基準を設けて要・不要を示して行く整理収納っていう事にことさら価値があるのです。一生役立つお片付けスキルを学べるのは当社セミナールームにて毎月開催中の整理収納アドバイザー2級認定講座、詳しくはこちらからどうぞ。https://anchors.me/contents_14.html
関連エントリー
-
 805/1000 鈍刀を磨く人生
「鈍刀を磨く。」という言葉を知った。自分を磨く、という言葉は少し気恥ずかしい。どこか意識が高い感じもするし、成
805/1000 鈍刀を磨く人生
「鈍刀を磨く。」という言葉を知った。自分を磨く、という言葉は少し気恥ずかしい。どこか意識が高い感じもするし、成
-
 807/1000 空き家と積雪
今日は立春ということで、日差しがほんの少しだけ柔らかく感じられる一日だった。今年は、凍てつくような寒さというほ
807/1000 空き家と積雪
今日は立春ということで、日差しがほんの少しだけ柔らかく感じられる一日だった。今年は、凍てつくような寒さというほ
-
 807/1000 最後の40代を丁寧に
鶴岡市から山形市までは、およそ90km。車で走ると、だいたい2時間ほどかかる。普段は庄内総合支庁に伺うことが多
807/1000 最後の40代を丁寧に
鶴岡市から山形市までは、およそ90km。車で走ると、だいたい2時間ほどかかる。普段は庄内総合支庁に伺うことが多
-
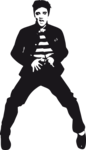 809/1000 ロックスターのサブスクマーケテイング
ロックスターには、つい神秘を求めすぎてしまう。ずっと不良で、心に傷を負っていて、社会にうまく回収されず、それで
809/1000 ロックスターのサブスクマーケテイング
ロックスターには、つい神秘を求めすぎてしまう。ずっと不良で、心に傷を負っていて、社会にうまく回収されず、それで
-
 811/1000 グルテンフリーと霜焼けの意外な関係
この冬、私にとってはっきりとした変化があった。毎年、足の指が凍傷レベルの地獄の霜焼けに悩まされてきた。歩くのが
811/1000 グルテンフリーと霜焼けの意外な関係
この冬、私にとってはっきりとした変化があった。毎年、足の指が凍傷レベルの地獄の霜焼けに悩まされてきた。歩くのが